ことばの発達はお母さんのお腹にいる時から始まっています。お腹から出てきた後も様々な刺激を得てことばを学習していきますが、「ことばの数を増やすにはどうしたらいい?」「どうやったら上手にお話しが出来るようになる?」悩まれる方もいるかと思います。
子どもは生活の中で自然とことばを習得していくと言われていますが大人から働きかけが必要不可欠です。今回は子どもと関わる時の大人側が意識する上手な声かけについて紹介します。
言語心理学的手法
子どもに対することばかけのポイントとして言語心理学的手法というものがあります。
言語心理学的手法は以下の7つがあり、下記においてそれぞれ解説していきます。
言語心理学的手法
ミラリング
モデリング
モニタリング
パラレルトーク
セルフトーク
リフレクティング
エキスパンション
ミラリング
子どもの行動をそのまま真似ること
例)子どもが指差しをしたら同じように指差しをする
子どもが口をパクパク動かしていたら同じようにパクパク動かす
モデリング
子どもにことばの見本を見せること
例)子どもがりんごを見ていたら「りんご」とことばで言って聞かせてあげる。
これは見たものとことばを一致することやことばの使い方を教えるものです。
ことばを育むために「ことばを教えましょう」と言われていますし、実践している人も多いと思います。この「ことばを教えましょう」と言われれることのほとんどがモデリングという技法を使っているのではないでしょうか。
モニタリング
子どもの声やことばをそのまま真似ること
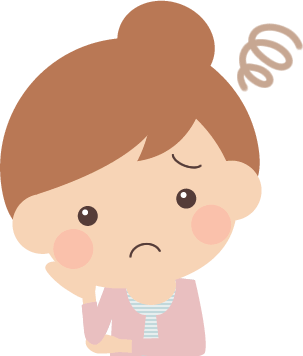
あー
あー

音声模倣は大人の声を子どもが真似をすることが大半ですが、モニタリングは子どもからの声やことばを真似るもの。
最近では人形に話しかけるとオウム返しのように人形が話しだすものが増えてきました。子ども自身の声をそのまま繰り返すと『同じ声が聞こえた』という楽しい気持ちを育むにはピッタリです。この楽しいという気持ちがあることによって発語意欲が掻き立てられます。
パラレルトーク
子どもの行動や気持ちをことばにすること
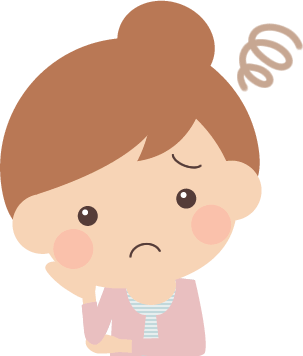
【りんごを指さす】👉🍎
りんごがあるねー

コミュニケーションはことばを話すだけではありません。子どもは指差しなどを用いてコミュニケーションを図ることもあります。
指差しの他に目線(アイコンタクト)で大人に訴えかけることもあります。そのような時は子どもが指差したものに対して「〜だね」と声をかけてあげると良いです
。
ことばで答えてあげることによって物の名前を覚えるというだけでなく、『指差しに反応してくれた』という喜びにつながります。
セルフトーク
大人自身の行動や気持ちをことばにすること
例)散歩中に可愛らしい犬を見かけたら大人が指差しながら「犬(わんわん)かわいいね」と子どもに声かける
リフレクティング
子どもの言い誤りを正しく言い直してあげること
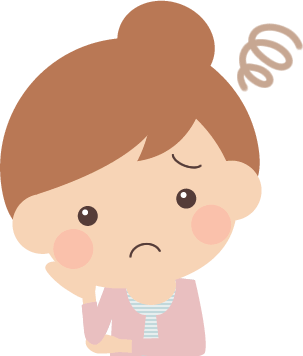
🐟たかなー
さかな(だね)

子どもが間違ったことばや発音を言ってしまった場合は、その間違いを指摘するのではなく「さかな(だね)」とさりげなく正しい言葉や発音を伝えましょう。
子どもから発したことばを指摘してしまうとお話しをする意欲が減ってしまうことがあります。
お話しが増えてきている段階の子どもは言い間違いを治すよりも、たくさんお話してもらうことを目標にしましょう。そのためにお話しやすい環境作りをしていきましょう。
エキスパンション
子どもの言ったことばの意味を広げて言ってあげること
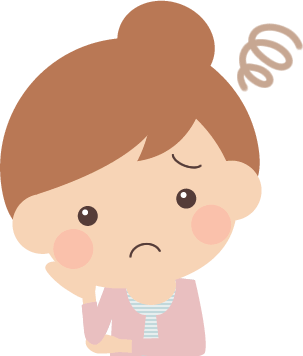
🍎 りんごー
赤いりんごだね

子どもが「りんご」と言った際に「りんごだね」と言うだけでなく、どのようなりんごなのか付け加えてあげることによってことばの使い方を習得することが出来ます。
「赤いりんごだね」は色+単語の組み合わせ。この他に大小+単語の組み合わせ「大きいりんごだね」や形+単語「丸いりんごだね」のような組み合わせを伝えると文章レベルでのお話しが上手に出来るようになるかもしれません。
まとめ
これらの声かけをすることで自然な流れでことばを身につけることが出来るのではないでしょうか。
「ことばの発達を促すためには?」と試行錯誤しながら子どもと関わりますが、子どもとのコミュニケーションを大人も一緒に楽しみながら日々の成長を見届けましょう。






